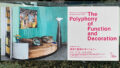「甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性」。甲斐荘楠音(かいのしょうただおと)は、大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家です。国画創作協会に出品された《横櫛》、映画業界に転身し手がけた時代劇衣装まで、全体像を展示します。
甲斐荘楠音の全貌の感想と解説!
○序章「描く人」。タイトルの《横櫛》は、河竹黙阿弥作「處女翫浮名横櫛(むすめごのみうきなのよこぐし)」からです。通称「切られお富」と言われ、恋人のために悪事を働くお富を主人公とします。楠音は義姉をモデルにして描きました。2点あります。
(005)《横櫛》1916(T5)年
(005)《横櫛》(上図)は、白粉(おしろい)を塗り、目の下と唇に濃い紅を引き、妖艶さをまといます。白い桜を散らした、紫地の羽織の右肩を外しています。水色の襟には天女が、黄色の上前(うわまえ)には、獅子と炎が描かれています。お富の内面を表しているようにも思えます。
左手は袖に隠し、右素足を前にしています。薄暗い牡丹図屏風の前で、着物の明るさが目をひきます。
(006)《横櫛》1916(T5)年
一方(006)《横櫛》(上図)は、目の上と唇に薄い紅です。絞り柄が描かれた藍色の羽織。水色の襟は絞り柄の格子模様。着物は朱色の地に、5点の役者絵がリズミカルに並んでいます。
茶系のストライプの帯の下がお富でしょう。紅を控えた化粧や、落ち着いた着物の色調で妖艶さは薄まります。しかし、役者絵を用いた機知に富んだ絵柄が、鑑賞者を歌舞伎の演目に引き込みます。
1918(T7)年に、国画創作協会に出品され、楠音の知名度を押し上げました。
(M-008-01)スクラップブック
甲斐荘楠音のスクラップブックにルノワールとか熱すぎるよね。岸田劉生もあった。 pic.twitter.com/0ygqjTKxg2
— KNM (@KNM2002) February 11, 2023
○第1章「こだわる人」には、(M-008-01)スクラップブック(上図)がありました。みうらじゅんでも大竹伸朗でもない、甲斐荘楠音のスクラップブックです(驚)。
モノクロの切抜きが多くを占め、数点のカラーがアクセントになっています。紙面には、いまのように拡大縮小ができない中、大きさの定まらない膨大な切り抜きが整然と貼り込まれています。興味の多くを留めておくための、並外れた几帳面さと熱量が伺われました。
(010)《島原の女(京の女)》1920(T9)年
切抜きは、全体を通して圧倒的に女性が多いです。それとは別に、キャプションが残されているものもあります。「”夏祭”の殺し場 竹之丞と猿之助」。夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)を演じるのは、六代目市村竹之丞と二代目市川猿之助でしょうか。
「ふしはら(罧原)堤」は、渡月橋から松尾橋まで続く堤です。この辺りは、時代劇のロケ地に使われます。眼光鋭い鎌倉時代の木彫「聖徳太子二歳像」。
(012)《舞ふ》1921(T10)年
「舞楽面『胡徳楽(ことくらく)』」。「通し矢」。日本画家「平福百穂(ひらふくひゃくすい)『荒磯(ありそ)』(近代日本の歩み展から)」。
「『四谷怪談』のけいこ、演技をつける小沢と大塚道子と仲代達矢」。小沢は俳優・演出家の小沢栄太郎でしょうか。
キャプションのないもので、喜多川歌麿 の『台所美人揃』のカラー図版。りんごを剥く女性の横顔。野球のヘッドスライディング。殺陣師(たてし)の練習風景などもありました。
【京都で見る、日本画と映画を越境した唯一無二の存在】https://t.co/eSdB7LHDnw
醜さも含めた人間の生々しさを描いた異色の日本画家・甲斐荘楠音。その美術館で二度目となる回顧展「甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性」が、京都国立近代美術館で開催中。会期は4月9日まで。 pic.twitter.com/hKLf4R6iAb
— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) February 14, 2023
甲斐荘楠音の全貌の図録をデサインマニアが分析!
「甲斐荘楠音の全貌」展図録。
自立する図録、久しぶりに買った。
スクラップブックも映画との関係も、スケッチ群も……とても貴重な資料としての一冊であると思ふ。表紙が《春》なのが良い。とても色っぽいし、春色が優しくて、女性の肌香の柔らかすら伝わってくる。 pic.twitter.com/W09SU3bv99
— 本屋しゃん (@honyashan) February 12, 2023
○カバーが掛けてあります。ビジュアルは(028)《春》(下図)です。ちょうど横位置の作品です。そのまま縦に半分に折ると、右開きの書物に用いることができます。
しかし、図録は縦組みで左開きです。そのため、女性の膝から下を画面の右に移しました。そのまま横にスライドさせるのではなく、上下の位置は金屏風の下のラインで合わせました。
裏表紙は継ぎ目をはさみ、左手と右足がほどよいバランスで同居しています。期せずして、ユニークな構成が生まれました(驚)。
○本体はターコイズブルーの地に、朱色でタイトルが記されています。《春》の着物の色から採りました。
(011)《幻覚(踊る女)》1920(T9)年
【きょう開幕】「甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性」展 京都国立近代美術館で4月9日(日)まで。
様々な領域を越境した稀有な表現者。その多彩な創作の全体像を示す注目の展覧会です。夏には東京ステーションギャラリーに巡回します。https://t.co/YdVMiZRr14 pic.twitter.com/pZhruFAEm7— 美術展ナビ (@art_ex_japan) February 11, 2023
○開くと、モノクロのポートレートが現れます。端正な顔立ちの青年が、浴衣姿で畳に腰を下ろし、右手を左膝に置きこちらを見ています。(041)《畜生塚》の前でポーズをする21歳の楠音です。
(001)《太夫と禿(かむろ)》は全体ではなく、三味線を持つ禿の肩から下のトリミングです。図録最初の掲載作品ですが、太夫と禿の表情はなくし着物の繊細な描写だけを見せます。

各章の扉には、太夫に扮する30歳の楠音のポートレート(上図中)。(021)《美人之図》の顔面の部分拡大は、紙面いっぱいで迫力があります。(028)《春》の部分拡大。コップを中心に、両手と着物がL字の構成をなしています。
(S-029)《スケッチ(黒猫と女)》。映画「新吾十番勝負」で用いた、(F-089-2)《衣装》の部分拡大。(S-057)《畜生塚の女》の上半身の部分拡大は、絹地が確認できます。
甲斐荘楠音の展示、作品そのものもゾクゾクきて良かったけど、楠音が衣装監修した旗本退屈男シリーズのなんでもとりあえず謎のをつけとくみたいなタイトルと、ご存知!三日月!お殿さま!みたいなキャッチコピーが面白すぎて展示してたポスターずっと眺めてた pic.twitter.com/kq2QWLHdNp
— 砂 (@snkj6) February 17, 2023
○第3章「越境する人」は、楠音が携わった映画のスチルも多くあります。うち2点が見開で掲載されています。(6)「歌麿をめぐる五人の女」(44)「旗本退屈男 謎の竜神岬」です。
歌麿をめぐる五人の女 #Utamaro and His Five Women, #KenjiMizoguchi (1946) pic.twitter.com/ImZA2HWoio
— Leticia García (@Ms_Golightly) September 18, 2014
前者は六代目坂東蓑助(ばんどうみのすけ)の演じる歌麿が、田中絹代の難波屋おきたの背中に、山姥と金太郎を描く様子を大きく捉えています(上図)。この刺青の下絵と時代考証は楠音によります。
(041)《畜生塚》1915(T4)年頃
あやしい絵展(@ayashiie_2021)開催中
本展最大の作品、甲斐庄楠音《畜生塚》。豊臣秀次の妻妾子30余人が処刑され、秀次と共に埋められた史実に取材したものです。重厚な裸体像はダ・ヴィンチやミケランジェロの表現を見て描いたといわれています。制作開始は楠音21歳の時。未完のまま残されました。 pic.twitter.com/r0YpuGfNwo— 東京国立近代美術館 MOMAT (@MOMAT_museum) April 12, 2021
○終章「数奇な人」。未完の大作(041)《畜生塚》(上図中)は八曲一隻(はっきょくいっせき)屏風です。京都瑞泉寺(ずいせんじ)に伝わる、豊臣秀次の一族が処刑された事件を題材に描かれました。
4見開き、8ページで掲載されています。最初の見開きは全体像です。見開きの下半分を埋めます。
次は一扇(いっせん)・二扇の部分拡大です。のどに掛かる両手で顔おをおおう人物は、(P-037)《畜生塚》の前でポーズする楠音のようです。部分拡大は、下描きの跡も分かり迫力があります。
※出展はありません
三扇・四扇の部分拡大は、右のふたりの顔が白く塗られています。人垣は、ミケランジェロの《バンディーニのピエタ》(上図)が参照されているようです。最後は五扇・六扇の部分拡大です。
ハードカバー/ W215mm × H290mm/ モノクロ・カラー/ 312ページ/ 日・英
3,200円(税込)

甲斐荘楠音の全貌の会場・巡回先はここ!
京都国立近代美術館

〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町26-1
Tel.075-761-4111(代表)
会期
2023年2月11日(土・祝)~4月9日(日)
休館日
月曜日
開館時間
10:00~18:00 ※毎週金曜日は20:00まで ※入館は閉館の30分前まで
アクセス
JR・近鉄~バス
○JR・近鉄「京都駅前」A1のりばから、市バス5番 銀閣寺・岩倉行「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
阪急・京阪~バス
○阪急「烏丸駅」阪急「京都河原町駅」京阪「三条駅」から、市バス5番 銀閣寺・岩倉行「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
○阪急「烏丸駅」阪急「京都河原町駅」京阪「祇園四条駅」から、市バス46番 祇園・平安神宮行「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
市バス他系統
○「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車徒歩約5分
○「東山二条・岡崎公園口」下車徒歩約10分
地下鉄
○地下鉄東西線「東山駅」下車、1番出口より徒歩約10分

東京ステーションギャラリー

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 丸の内北口 改札前
Tel.03-3212-2485
会期
2023年7月1日(土)~8月27日(日)
開館時間
10:00~18:00 ※金曜日は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで
休館日
月曜日(祝日の場合は翌平日) 、年末年始、展示替期間
アクセス
丸の内北口 改札前